朝起きても体が動かない。
やらなきゃいけないことが山積みなのに、気持ちがついてこない。
そんな「何もしたくない日」、ありますよね…。
多くの人はこの状態を「怠けている」と感じ、
自己嫌悪してしまいます。
しかし仏教では、
こうした心の状態も大切なサインだと考えます。
この記事を、
「今日は何もしたくない」
と思っているあなたに読んでほしいです。
何もしたくない日は”心の雨の日”
仏教では、
心の働きを「五蓋(ごがい)」という5つの状態に分類します。
- 貪欲蓋(とんよくがい):欲しがる心、物事への執着
- 瞋恚蓋(しんにがい):気に入らないことに対する怒り
- 惛沈睡眠蓋(こんじんすいめんがい):心が重く沈んだりだるさを感じたりする状態、または眠りこけてしまう状態
- 掉挙悪作蓋(じょうこおさがい):心が高ぶったり、後悔の念に囚われたりする状態
- 疑惑蓋(ぎわくがい):自分や他者を信じられず、疑いを持つこと
「蓋」とは、本来清浄であるはずの心を覆い隠し、
善い行いを妨げるもの=煩悩を意味します。
この五つの煩悩に妨げられると、
心は散乱し、集中力や悟りへの道が閉ざされてしまいます。
この中でも惛沈睡眠蓋は
心のエネルギーが低下してぼんやりしている状態です。
ただ、これ自体は悪ではなく、
「今は心が休もうとしているだけ」と理解することが大切なのです。
雨の日に無理に外で走り回らないように、
心が雨の日ならば休ませることも必要です。
お釈迦さまは弟子たちに対し、
(インドの)雨期にあたる3か月間は一か所にとどまり、
修行と休息に専念する「安居(あんご)」を指導しました。
これは「休むことも修行の一部」という考えを表しています。
自分を責めないための言葉
仏教の言葉に、次のようなものがあります。
自己を愛するがゆえに、悪をなすなかれ
(ダンマパダ)
ここでいう「悪」とは、
他人を傷つける行為だけでなく、
自分をむやみに責めることも含まれます。
「何もできないわたしはダメだ」と思うこともまた、
自分に対する暴力であるとお釈迦さまは説いています。
何もできない日は、まず
「わたしは今、休む必要があるんだね」
と心に声をかけてみましょう。
これだけで、少しずる肩の力が抜けていくのを感じるでしょう。
あなたは本当は何を求めている?
「何もしたくない」の奥には、
実はさまざまな感情や欲求が隠れています。
その”本当の気持ち”を知るために、
書き出しワークをやってみましょう。
- 最近、どんなことが疲れた?
- 誰のためにがんばりすぎた?
- 本当はどんな時間がほしい?
例えば…
仕事が疲れた
→業務よりも人間関係に疲れた
→無責任な人が多くてイライラする
→物理的に距離をおきたい(ひとりになりたい)
こうして見つけた欲求は、
次の休みの日に少しずつ満たしてあげると
心のエネルギーが回復してきますよ。
”中道”の考え方でバランスをとる
「何もしたくない」と思っていても、
何もしない日が続くとさすがに不安になりますよね…。
ですが仏教では、「中道(ちゅうどう)」が大切だと説きます。
中道とは、
怠けすぎることと、がんばりすぎることの
どちらにも偏らない生き方です。
何もしたくない日には、以下のような「小さな行動」を選ぶとバランスがとれます。
- 布団の中で深呼吸を3回する
- カーテンを開けて光を入れる
- 好きな音楽を1曲だけ聴く
- 温かいお茶をいれる
こういった些細なことでも、
続けることで心が少し動き出しますよ。
お釈迦さまの休息の教え
仏典には、お釈迦さまが疲れた弟子に
森の中で静かに坐って心を整えよ
と語った場面があります。
お釈迦さまは無理に続けるよりも、
まず心を回復させることが大事だと伝えています。
現代でも同じです。
「今日は休もう」と決めて、
スマホも手帳も閉じて、ただゆっくり過ごす。
それだけで、次の日の行動力がまったく違ってくるはずです。
休むことも立派な行い
何もしたくない日を「ダメな日」と見なさず、
心のメッセージとして受け取る。
それが仏教的な視点です。
休むことは怠けではなく、心の安居
自分を責めず、やさしい言葉をかける
小さな行動からバランスを取り戻す
お釈迦さまの言葉を最後に紹介します。
疲れたなら、立ち止まりなさい。休むこともまた道である
今日は何もしない日でもいい。
あなたが心を回復させるその時間が、
明日を生きる力になりますように。

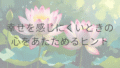
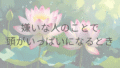
コメント