「幸せになりたい」と願っているのに、
なぜか心が満たされないときってありますよね。
周りの人は幸せそうに笑っているのに、
自分だけ取り残されたように感じることもあるでしょう。
仏教では、幸せは外からもらうものではなく、
心の内から生まれるものだと説かれています。
今回は、幸せを感じにくいときに役立つ仏教の視点と、
日常でできる実践をお伝えします。
渇愛に気づく
お釈迦さまは、人が苦しむ原因は、渇愛(かつあい)
つまり「もっと欲しい」という強い欲求にあると説きました。
- もっとお金があれば幸せになれる
- もっとやせれば好きになってもらえる
- もっと認められれば安心できる
こうした「もっと、もっと」という気持ちが強いほど、
幸せは遠ざかります。
まずは「いまの自分が感じている渇き」に気づきましょう。
紙に書き出すだけでも、
心の中のモヤモヤが整理されていきますよ。
”足るを知る”で心を満たす
仏教には「知足(ちそく)」という美しい言葉があります。
これは「足るを知る」、
つまり「いまあるもので満ち足りていると感じる心」のこと。
たとえば、いまあなたが座っている椅子…
座る場所があるだけで、ひとつの幸せです。
温かいお茶を飲める、屋根の下で眠れる…
それだけでも十分にありがたいことなのです。
お釈迦さまはこう言いました。
「足ることを知る者は富めり」
(ダンマパダ)
”持っているもの”に意識を向けることで、
心が少しずつ満たされていきます。
幸せを感じにくいときの実践ワーク
では実際に、
幸せを感じにくいときにできるおすすめワークを紹介します。
3つの感謝を書き出す
きょうあった小さな出来事を思い出して、
感謝できることを3つ書きましょう。
例えば…
- 天気が良くて気持ちが良かった
- 朝からおいしいコーヒーをゆっくり飲めた
- 職場の人がフォローしてくれた
- お客さんに「ありがとう」って笑顔で言ってもらえた
- 子どもの機嫌が良く、家事もスムーズにできた
- 晩ご飯がおいしかった
- きょうも一日が無事に終わった
些細なことで良いのです。
そんな小さな感謝が、幸せを呼び戻してくれます。
慈悲の瞑想をする
慈悲の瞑想は、仏教の代表的な実践です。
難しいことはありません。
心の中で次の言葉を唱えてみましょう。
わたしが幸せでありますように
わたしが安らかでありますように
大事なのは、”わたし”を主語にすることです。
そして自分に軸を置くことに慣れてきたら、
つぎに大切な人、そして少し苦手な人にも
この言葉を向けてみます。
すると少しずつ心があたたまり、
世界とのつながりを感じられるでしょう。
”比べる心”を手放す
幸せを感じにくいとき、
多くは「誰かと比べている」状態です。
SNSを見ると、
他人の成功や楽しそうな様子が次々と流れていますよね。
他人の幸せを羨み、自分と比べ、
そのたびに「自分は足りない」と思ってしまうのです。
仏教では「無我(むが)」の考え方を大切にします。
無我とは仏教における主要な教えの一つで、
固定的な自我(自己)の存在を否定する概念のことです。
それだけを聞くとネガティブな印象がありますが、
そうではありません。
仏教では
”わたし”の苦しみの根源は、自己への”執着”であると説いています。
「無我の境地」という言葉がありますが、
これは自己への執着を離れた、”無心の心”の状態に達することを指します。
自我の存在を否定することで、
執着から解放され、苦しみを乗り越えられるとされていますよ。
”わたし”というものは固定された存在ではなく、さまざまな要素の集まりにすぎない
だから他人と比べる必要はなく、
あなたはあなたで十分に価値があるのです。
”中道”でバランスをとる
”幸せ”を追いかけすぎると、
疲れてしまいませんか?
でも逆に「もう何をしても幸せになれない」と
諦めてしまうのも苦しいんですよね。
仏教が教える「中道(ちゅうどう)」は、どちらかに偏らない生き方です。
ちょっとだけがんばる
ちょっとだけ休む
”0か100”ではなく、完ぺきを目指しすぎない。
そんな小さな調整を続けることで、
心が整っていきますよ。
幸せは”いまここ”にある
幸せを感じにくいときは、
外の世界を追いかけるよりも、内側に目を向けてみましょう。
- 渇愛に気づく
- 足るを知る
- 感謝を書く
- 慈悲の瞑想をする
- 比べる心を手放す(無我)
- 中道でバランスをとる
お釈迦さまの言葉にこんなものがあります。
幸せは外からではなく、心の中に生まれる
あなたの心の中に、幸せの種はすでにあるんです。
あなたの心が少しでもあたたかくなるように、
きょうはその芽に水をあげてみませんか?
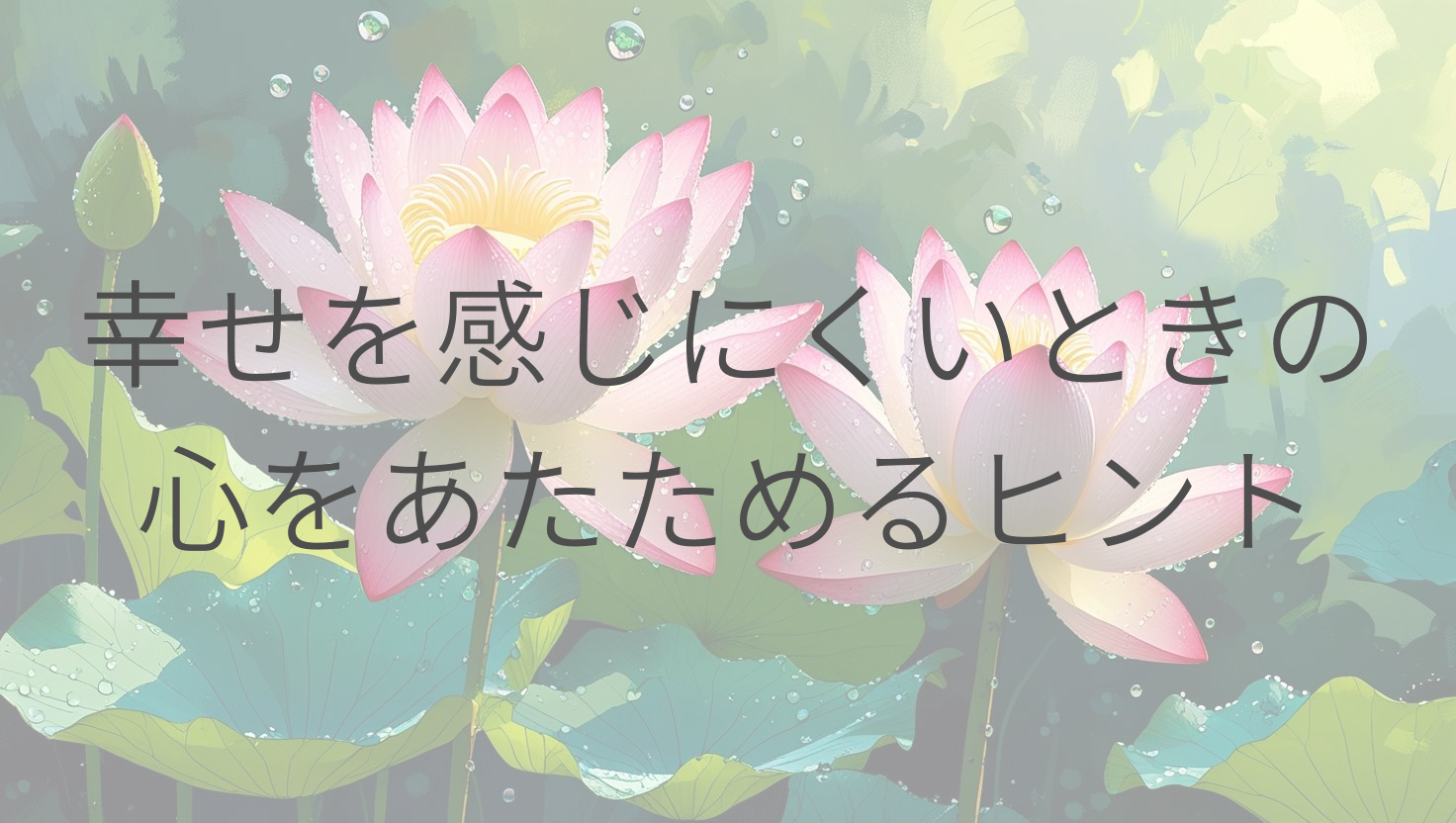
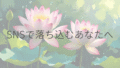
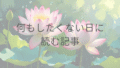
コメント