~ブッダが語った「ほんとうの休息」とは~
「ちゃんと休んだのに、まだつらい」と感じるとき
週末に何もせずに過ごした。
人と会わず、のんびりした。
早く寝たし、食事もとった。
それなのに、月曜日の朝。
「また疲れてる…」「元気が戻ってない」
そんなふうに感じてしまう日が、誰にでもあるものです。
(わたしもしょっちゅうです)
それは「心が休めていないサイン」
ブッダは、休息についてこんな教えを残しています。
「休むとは、動きを止めることではなく、執着から離れること」
―『スッタニパータ』
この言葉が示しているのは、身体の休息だけでは足りないということ。
わたしたちはときに、休んでいるようでいて、
心の中ではこんなことを考え続けています。
- 「休んでいる間に、みんなは頑張っているかも」
- 「ちゃんと回復しなきゃ」
- 「明日からまた動かなきゃ…」
そんな「休まらない焦り」が、
心の深いところで疲れを増やしているのです。
心理学でも言われる「感情の疲労」
心理学では、「休んでも疲れが取れない状態」のひとつとして、
感情労働・精神的ストレスによる蓄積疲労が挙げられます。
例えばこんな状態…
- 気を張り続けたあと、気が抜けなくなっている
- 自分を責め続けていて、心が落ち着かない
- 他人に合わせることに疲れている
- 「休んでいい」と思えていない自分がいる
この状態では、たとえ布団の中にいても、
交感神経(緊張)が優位になったままで、
本当の意味で「休息モード」になれないのです。
ブッダが語る「ほんとうの休息」
「心を手放したとき、人は休息を知る」
―『ダンマパダ』
ブッダは、真の休息とは「なにもしないこと」ではなく、
「頑張らなきゃ」「こうあるべき」という心の荷物を一時下ろすこと」だと説きました。
それは、何かを得ようとするのではなく、
「今のままの自分を、そのまま受け入れる」時間とも言えるでしょう。
「回復しよう」としなくてもいい
疲れているのに休んでも元気にならないとき、
さらに追い詰めてしまうのはこんな思いです。
- 「休んだのに回復できないわたしはダメだ」
- 「こんなことでへこんでるなんて、情けない」
- 「このままだと、みんなに迷惑かける…」
でも、そんなふうに回復を義務のようにしてしまうと、さらに疲れてしまうのです。
むしろこう言ってあげてください。
「元気じゃなくても、今の自分で大丈夫」
「がんばらなくても、あなたの価値は変わらないよ」と…。
小さな「休み方」を見直してみる
①スマホを見ない時間を15分つくるだけでも、脳は静かになります。
②信頼できる人に話す/紙に書いてみるだけでも、心が軽くなります。
③「ただボーッとする」「空を眺める」ことを自分に許す。
これらは、心の奥に届く“ほんとうの休息”の入り口です。
休むことは、立ち止まることではない
ブッダは、こんなふうにも語っています。
「雨が止むまで、蓮の葉はじっと待つ」
―仏教説話より
無理に元気を出そうとしなくていい。
流れに逆らわず、静かに待つこともまた、回復の一部です。
あなたが元気になれないのは、あなたが怠けているからではありません。
むしろ、人知れず頑張ってきた証拠です。
今は、「元気にならない自分をそのまま受け入れる」という休み方を
やさしく、自分に許してあげてほしいと思います。
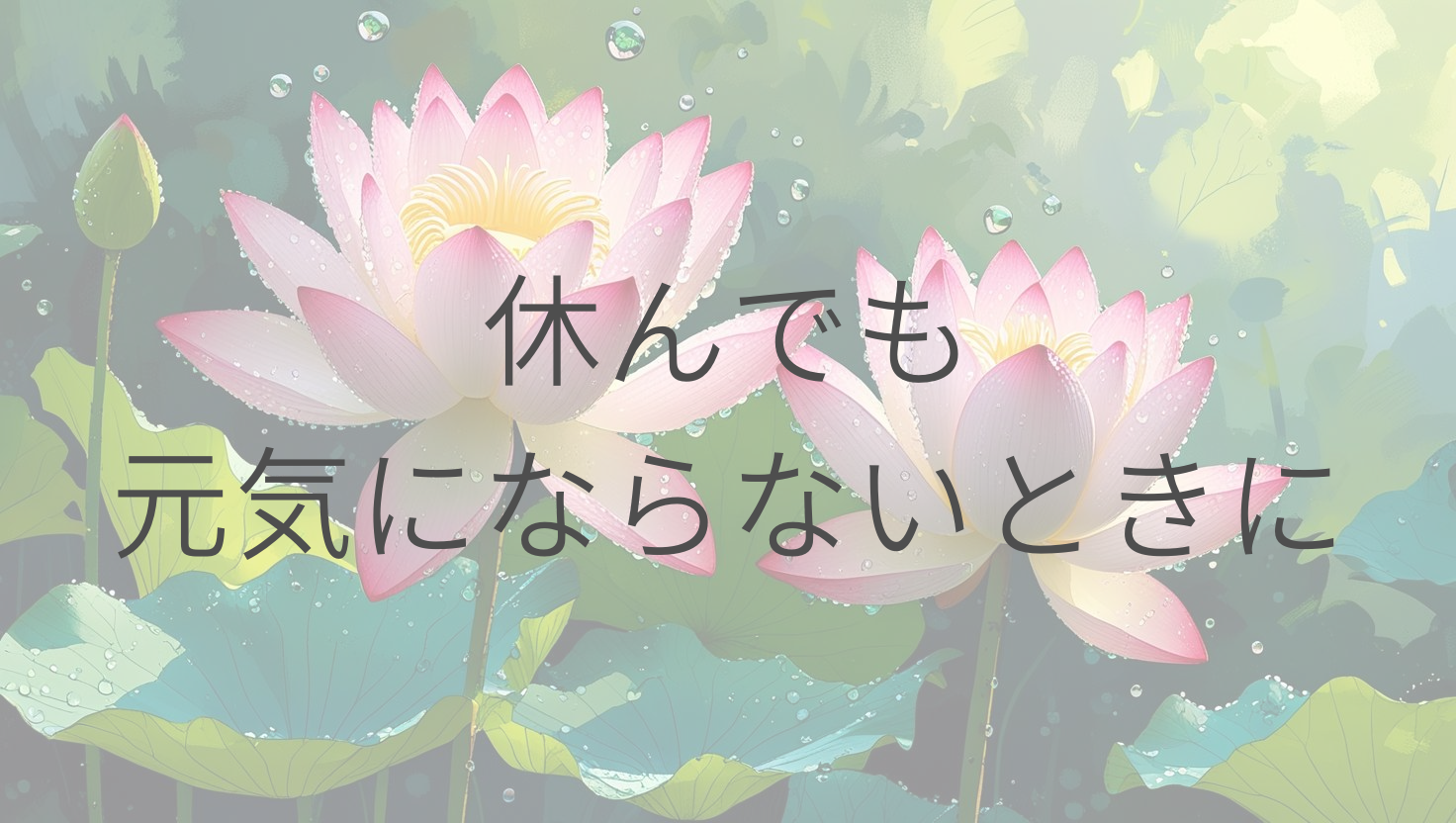
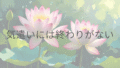
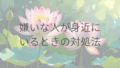
コメント