瞑想とは、心を静める練習です。
仏教では「サマタ(止)」と「ヴィパッサナー(観)」
というふたつの瞑想があります。
サマタ瞑想は、
呼吸や音などに意識を集中して心を安定させるもの。
ヴィパッサナー瞑想は、
心に浮かんだ感情や思考を「ただ観察する」ものです。
どちらも、
苦しみの根本原因を見極めるための大切な修行とされています。
この記事では瞑想の目的や効果、マインドフルネスとの違いを解説しながら
きょうからできる瞑想の方法をご紹介します。
瞑想の目的
瞑想のゴールは「リラックス」ではありません。
もちろん、深いリラックスが得られることもありますが、
本質は「自分を知る」こと。
仏教では、
人の苦しみの多くは、”気づかないまま心が反応してしまう”ことから生まれる
と説きます。
たとえば誰かにきつい言葉を言われたとき、
反射的に怒ったり、落ち込んだりしてしまいますよね。
瞑想は、その反射の前に「今、怒りが生まれた」と気づく練習です。
気づきが深まると、
怒りに引きずられずに選択できるようになります。
マインドフルネスとの違い
最近はマインドフルネスという言葉をよく聞きますが、
これは仏教のヴィパッサナー瞑想をもとに、
宗教色をなくして現代生活に取り入れやすくしたものです。
マインドフルネス:ストレス対策や集中力向上、メンタルヘルスの改善など、実用的な目的にフォーカス
仏教の瞑想:悟り(苦しみの根本原因を理解し、自由になること)を目指す、より深い精神的探求
つまりマインドフルネスは「入り口」、
仏教の瞑想は「奥の院」のようなイメージ。
まずマインドフルネスから始め、
そこからさらに深めていくことも可能です。
瞑想の効果
わたし自身、
瞑想を続けることで「感情の揺れが少なくなった」と感じています。
仏教では「心が整えば世界も整って見える」と言われます。
これは単なる比喩ではなく、実は脳科学的にも裏づけがあるんですよ。
瞑想を習慣にすることで得られる効果として、
- イライラや不安にとらわれにくくなる
- 人間関係でカッとしにくくなる
- 集中力や判断力が上がる
- 自分や他人にやさしくなれる
などの変化が起こりやすいと研究でも示されています。
またブッダは心を「サルの群れ」に例えました。
サルは次々に枝から枝へ飛び移り、落ち着きません。
わたしたちの思考も同じ。
過去や未来を行ったり来たりします。
瞑想はそのサルをしずかに見守る練習です。
サルはすぐには止まりませんが、
見守り続けているとやがて落ち着いて枝に座るようになります。
きょうから実践|瞑想のやり方
瞑想の基本的なやり方は、全部で5ステップです。
- 静かな場所に座る
- 背筋をまっすぐにし、目を閉じるか半眼にする
- 呼吸に意識を向け、「吸っている」「吐いている」と心の中で言葉を添える
- 雑念が浮かんだら「考えていた」と気づき、また呼吸に戻る
- 最初は3分から始め、慣れたら10分、20分と伸ばしていく
瞑想で大事なのは「雑念を消そうとしない」こと。
雑念は敵ではなく、ただ観察する対象と捉えましょう。
続けるためのコツと日常への応用
ここまで瞑想の目的や効果、方法を詳しくご紹介しましたが、
でも「最初は3分から」と言っても、それすら続かないかも…
上手くできなかったらどうしよう…
あなたはいまそんな風に感じているかもしれませんね。
そんなあなたに、
瞑想を続けていくためのちょっとしたコツをご紹介しますよ。
- 時間を決める
- 完ぺきを求めない
- 記録する
まず、「朝起きたら」「夜寝る前」など、いつでも良いので
一日の中に”瞑想の時間”を作りましょう。
「気が向いたらやる」のではなく、
生活のリズムの中に瞑想を取り入れることを決めると、
上手く習慣化しますよ。
また、完ぺきを求めないことも続ける上で大事なことです。
「きょうは集中できなかったな…」で良いのです。
毎日座ることに意味があると考えましょう。
さらに、瞑想した実績をカレンダーなどに記録すると
「できた」結果が見えるので達成感に繋がります。
まとめ
瞑想は特別な人だけの修行ではありません。
忙しい現代に生きるわたしたちにこそ必要な、心を整える技術です。
マインドフルネスから始めてもいいし、
仏教の教えにふれながら深めていくのもいい。
心をしずめる練習を続けていくと、世界がやわらかく見え、
他人やあなた自身を責める気持ちも少しずつほどけていきますよ。
きょう、3分だけでも良いのです、
静かな場所を見つけて、呼吸に意識を向けてみませんか?

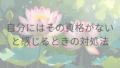
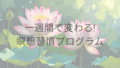
コメント