~だからこそ、自分を大切にする勇気を~
ずっと気を遣っているのに、なぜか報われない
職場でも、家庭でも、友人関係でも…
「大丈夫かな?」
「嫌な思いをさせていないかな?」
と、人の顔色をうかがいながら、
つい気を遣ってしまう。
気づけば、誰よりも気を配り、誰よりも疲れているのは、自分。
でも、ふと思うのです。
「どうしてわたしは、こんなに気を遣ってばかりなんだろう?」
「誰も気づいてくれないし、感謝もされないのに」
気遣いは美徳でもあり、呪縛にもなる
気遣いができる人は、心が繊細で、
人の痛みに気づける優しさを持っています。
それは間違いなく、美徳であり、強さでもあります。
でも、ブッダはこんな言葉を残しています。
「水を汲んでも、器がなければこぼれてしまう」
―仏教説話より
他人の気持ちばかりを汲み続けて、
自分という器が空になってしまっては、本末転倒です。
気遣いが終わりのないものになってしまうのは、
「自分の気持ちを後回しにする習慣」が根づいてしまっているからかもしれません。
心理学で見る「気遣い疲れ」
心理学では、過剰な気遣いの傾向を「他者志向性」や「過剰適応」と呼びます。
特徴は、
- 自分のニーズより、他人の気持ちを優先してしまう
- 「嫌われたくない」「波風を立てたくない」気持ちが強い
- 断れない、頼まれるとNOが言えない
- 他人の感情に敏感すぎて、自分が疲れ果てる
こうした状態が続くと、心がすり減っていく感覚や、
「わたしは何のために生きているんだろう」
と虚しさを抱えることにもつながります。
ブッダの言葉が教えてくれる「ちょうどよい距離」
ブッダは「中道(ちゅうどう)」という教えを大切にしていました。
中道とは、極端に走らず、偏らず、バランスを取ること。
「愛するとは、相手と適切な距離を保つことだ」
―『スッタニパータ』
過度な気遣いは、相手を思うことではなく、
自分の不安を埋めるための行動になってしまうこともあります。
だからこそ、「人のため」と「自分のため」のバランスをとることが、
ほんとうの意味でのやさしさにつながるのです。
気遣いをやめるのではなく、「分けあう」ものにする
気遣いとは、相手とのあいだで生まれるものです。
一方的に与え続けるのではなく、
ときには相手に委ねたり、任せたり、
「わたしもあなたを信じているよ」という距離感をもつことが大切です。
「気づかれないやさしさもある。けれど、気づかれないまま消えてしまってはいけない」
―仏教の例話より
自分の気遣いが空気のように
当たり前になってしまう前に、
自分の思いも言葉にして、
相手と分かち合う努力が必要です。
自分を大切にする小さな練習
気遣いが習慣になっている人は、
「自分を後回しにすること」が当たり前になっています。
そんなあなたにおすすめの言葉の切り替え
| つい言ってしまう言葉 | 替えてみる言葉 |
|---|---|
| 「なんでもいいよ」 | 「わたしは〇〇がいいかな」 |
| 「大丈夫です」 | 「ちょっと疲れてるので、また今度」 |
| 「わたしがやっておくよ」 | 「できることがあれば教えてね」 |
小さなひとつでも、
自分を主語にした言葉を使ってみる。
それが、自分を大切にする第一歩です。
少しずつでも、日常生活でチャレンジしてみませんか?
気遣いにも、休息が必要
気遣いには終わりがありません。
どこまでも、もっと、もっとと続いていきます。
だからこそ、「今日はここまで」と決める勇気が必要なのです。
ブッダはこう語っています。
「川の流れも、岩に当たれば止まる。その静けさの中にこそ、知恵が宿る」
―『ダンマパダ』
あなたがいつも気を配っていること、
誰かはきっと見ていなくても、
そのやさしさは、
あなた自身にまず向けられるべきものです。
終わりのない気遣いの中で、
「自分をいたわる」という選択肢を、どうか忘れないでくださいね。

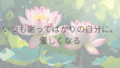
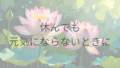
コメント