私たちは、日々たくさんの情報や刺激に囲まれながら生きています。
スマートフォンの通知、誰かの言葉、仕事の締め切り・・・
それらが同時に押し寄せてくると、心はどこか落ち着かず、
何かに集中できなくなってしまいます。
そんな現代のわたしたちに、
静かに語りかけてくれるのが「一心(いっしん)」という仏教の言葉です。
それは「心をひとつに定めること」、
つまり「いまここ」に心を向ける生き方を意味しています。
この記事では一心の意味と、一心に生きるヒントを解説します。
一心とは、心をひとつにすること
「一心」という言葉は、仏教の経典にたびたび登場します。
たとえば『法華経』には、
一心に聴聞(ちょうもん)せよ
という言葉があります。
これは「心を散らさず、ただひとつのことに集中しなさい」という教えです。
ブッダは、心は本来「風のように揺れ動くもの」だと説きました。
だからこそ、その心をひとつにまとめることが、修行の第一歩なのです。
心理学の言葉でいえば、「一心」とは「フロー状態」に近いかもしれません。
ひとつのことに深く没頭しているとき、
わたしたちは不思議と疲れを感じず、むしろ心が落ち着いていきます。
そのとき、心は「いまこの瞬間」にまっすぐ向かっているのです。
一心が乱れるとき
しかし、現実の生活ではなかなか「一心」でいることは難しいものです。
たとえば、仕事中にスマホの通知が鳴ったとき。
つい気になってしまい、頭の中は
「今やっていること」と「別のこと」が混ざり合ってしまいます。
人間関係でも同じです。
誰かの言葉を思い出してモヤモヤしているとき、
心はその場にありません。
体はここにあっても、心は過去の出来事へと飛んでいってしまいます。
ブッダは、そんな心の状態を「猿心(えんしん)」と呼びました。
猿が木から木へと飛び移るように、心があちこちに揺れ動く様子です。
そしてこの「心の落ち着かなさ」こそが、
苦しみを増やす原因だと説いたのです。
一心に生きるための練習
では、どうすれば心を「一心」に保てるのでしょうか。
ブッダは『法句経』の中で、こう語っています。
心は容易に揺れ動くが、訓練すれば静まる
この「訓練」とは、瞑想や呼吸の観察のことを指します。
たとえば、朝の数分だけでも
「呼吸に意識を向ける」練習をしてみるとよいでしょう。
息を吸うときは「吸っている」と、
吐くときは「吐いている」と、ただ感じるだけ。
それだけで、心は少しずつ”いま”に戻ってきます。
また、日常の中でも「一心」を育てる方法はたくさんあります。
- ひとつの作業を丁寧に行う(マルチタスクをやめる)
- 誰かと話すときは、相手の言葉に「心を傾ける」
- 食事中は、味や香り、食感をゆっくり味わう
小さな瞬間でも、
意識をひとつに向けることが「一心」の練習になります。
一心と安心
「一心」に生きることは、同時に「安心(あんじん)」を得る道でもあります。
「安心」とは、仏教でいう「安らかな心の状態」。
未来を案じず、過去を悔やまず、”いま”をそのまま受け入れる心です。
わたしたちはつい、「もっと良くしよう」「まだ足りない」と、
心を分散させてしまいます。
もっと良くしよう、まだまだ足りないと思うこと自体は、
決して悪い事ではありません。
それを自分のエネルギーに変えて、よりレベルアップしていけるなら、
とても良いことだと思います。
ただ、もっと良くしよう、まだ足りないという思いには、キリがありません。
その思いがあなた自身にとってプレッシャーになっていると、
心は”いま”に集中できていない状態かもしれません。
でも、「”いま”できることに一心になる」と、
不思議と焦りは消えていきます。
”足るを知る生き方”にもつながるこの心のあり方が、
ブッダの教える「中道」とも響き合っているのです。
またこちらの記事では、”足るを知る生き方”をテーマに、さらに詳しく解説をしていますよ。
おわりに
「一心に生きる」というのは、
完ぺきに集中して生きるということではありません。
むしろ、散らかった心に気づいたとき、
また静かに「いまここ」に戻る。
その繰り返しの中で、少しずつ心が穏やかに育っていきます。
誰かの言葉に揺れた日も、うまく集中できなかった日も大丈夫
気づいた瞬間こそが、すでに「一心への道」の上にいる証です。
今日もほんの少しだけ、心をひとつにして、”いまこの瞬間”を感じてみましょう。
きっとその時間が、あなたの心を静かに満たしてくれるはずです。

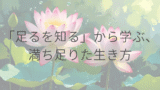
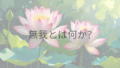
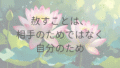
コメント