突然ですが、「わたし」という存在は、
どこまでがほんとうの「わたし」なのでしょうか。
ブッダが説いた「無我(むが)」という言葉は、
一見するとむずかしく感じられます。
ですがこの教えにふれると、
私たちがふだん抱えている「生きづらさ」をやわらげるヒントが見えてきます。
心理学でも「自己」というテーマは深く研究されていて、
「無我」の考え方と重なる部分があります。
この記事では、ブッダが説いた「無我」と、
心理学で用いられる「自己」をそれぞれ解説しながら
日常の中で無我の視点を取り入れるヒントをご紹介します。
ブッダの言葉にある「無我」
ブッダはこう語っています。
すべてのものは無我である。
これを智慧をもって見るとき、人は苦しみから離れる
『ダンマパダ』より
「智慧(ちえ)」とは一般的な知識という意味だけではなく、
物事の真理や本質を見極め、
様々な経験から得られる気づきや、深い理解のことを指します。
そして「無我」とは、
「決して変わらない固定された自分は存在しない」ということを示しており、
すべては絶えず変化する現象の集まり(縁起)であると理解することです。
この「無我」の概念は、自己への執着から解放され、
より自由な生き方へと導くことを目指します。
心理学が語る「自己」
心理学でも「自己」や「アイデンティティ」は大切なテーマです。
たとえば発達心理学では、人は成長の過程で
「自分はこういう人間だ」という感覚(アイデンティティ)をつくり上げていくと考えます。
しかし、その「自己」も環境や経験によって変わります。
また、認知行動療法のなかでは「思考と自分を切り離す」練習が行われます。
ある考えが頭に浮かんでも、それが自分そのものではなく、
「ただの思考」として距離をとるのです。
これは「無我」に通じる実践といえるでしょう。
つまり、心理学でも「わたしは変わらないもの」という考え方はむしろ
苦しみを生むことがある、とされているんです。
「無我」を日常に活かす工夫
ではわたしたちはどうやって「無我」の視点を日常で活かせるでしょうか。
この章では、日常の中で無我を活かすヒントを3つご紹介しますね。
思い込みを手放す
「わたしはこういう人間だから」
という決めつけを、きょうはゆるめてみましょう。
たとえば「人見知りだから初対面の人と話すのは苦手・・・」と思っても、
実は相性の問題だけで、案外、会話がはずむこともあるかもしれません。
「食わず嫌い」をやめて過ごしてみると、
「わたしって案外こういう人間なんだ」と、
新しい自分に出会えるかも知れませんよ。
瞑想やマインドフルネスを実践する
「瞑想」とは、心を静める仏教の修行のひとつです。
瞑想で呼吸に意識を向けたり、頭に浮かんだ考えを
「そういう思考があるな」と眺めたりすると、「無我」に近い感覚が得られます。
こちらの記事では瞑想についてさらに詳しく解説し、
実践方法も紹介しています。
過去の自分に囚われない
昔の失敗や弱点を、”いま”の自分まで背負い続ける必要はありません。
過去の失敗やあなた自身の弱点は、「これからの糧」として受け入れてみましょう。
例えば、
- 過去の自分を責めずに労わる
- 感情に名前をつける
- 失敗を学びと捉える
- 完ぺきを目指さない
人は変わり続ける生きものです。
過去の自分に囚われず、「いま、ここ」=「無我」に意識を向けると
自分を「固定した存在」と思わず、
「変化のなかで生きる存在」と受けとめる助けになります。
まとめ
「無我」は「自分を消すこと」ではなく、
「変わらない自分は存在しない」と理解することです。
それは「自分はいつも変わり続けていい」という自由を与えてくれます。
また心理学も同じように、「自己」を固定化せず、
思考や感情とほどよい距離をとることをすすめています。
ブッダのことばに耳を傾け、
心理学の知見と合わせてみると、わたしたちの心は少し軽くなります。
「わたし」に縛られすぎず、ゆるやかに生きていく。
それが「無我」が示す大切な知恵なのかもしれませんね。
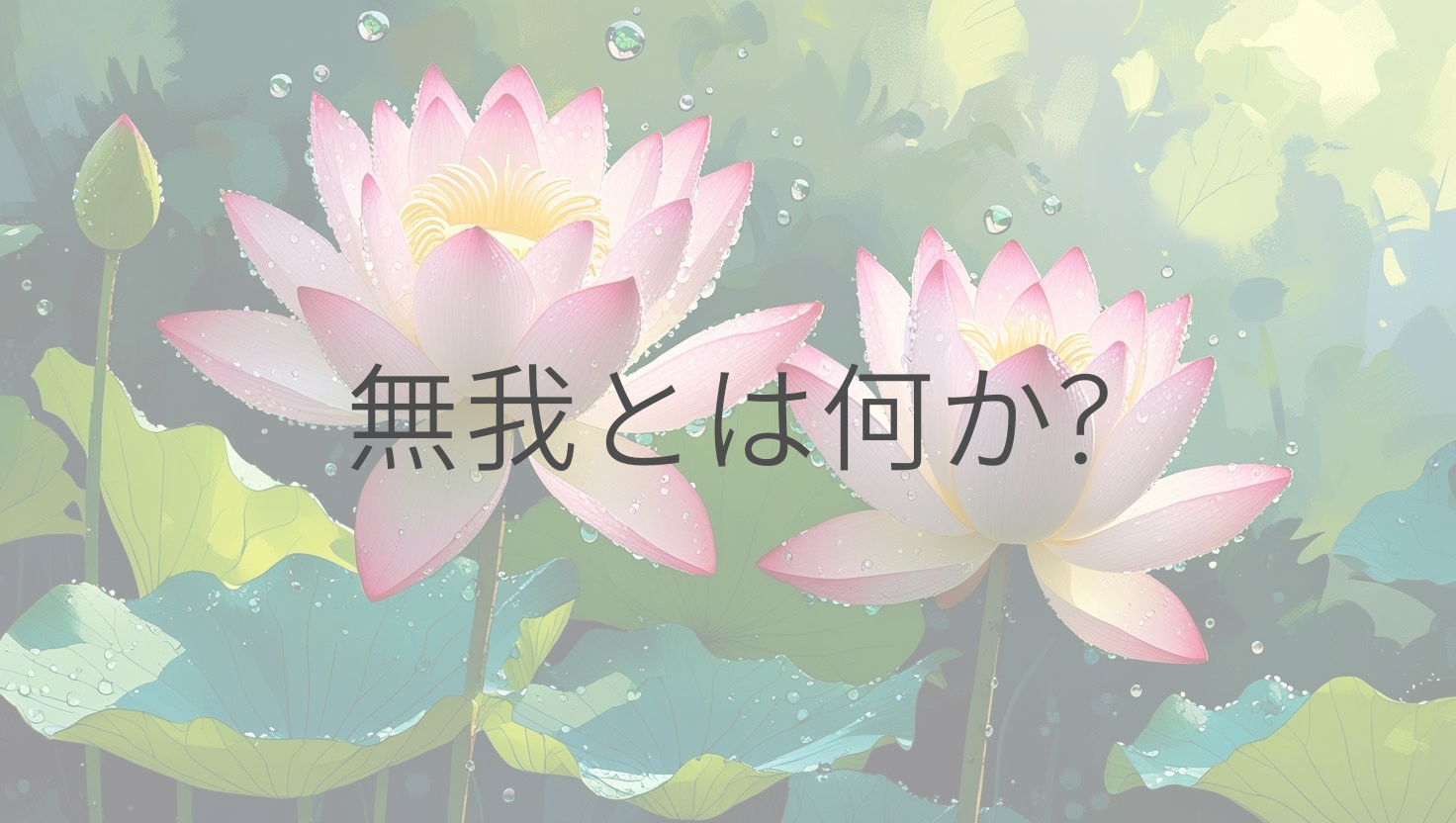

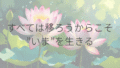
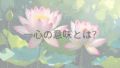
コメント